なぜ外部フィルター?
水流問題
先日から気になってる「メダカの飼育の水流問題」。ビオトープの用に水流も無くろ過装置もない環境でもメダカは生きることが出来るようです。
しかし、その様な環境でも生きることが出来るのと快適な環境は別物だと思います。水質は良いほうが良いだろうし、酸素量も適度に多いほうが良いと思っています。
水流に関してもまったくない方が良いような事を言うYouTuberもいますが、自然でメダカがどの様な場所でどのように生活しているのか見たこと無いのだろうな・・と思っています。
アクアポニックス側にポンプを入れビオトープ側に水を送っています。しかし、シャワー的な物がまだ届いていません。Amazonはうっかりすると中国発送で1ヶ月以上かかったりします。
今はホースのままでビオトープの水槽はホースの口の部分はそれなりの水流があります。
4.2Wの水中ポンプなので水量は大したことがないのですが、メダカも流石にホースの口のあたりを泳ぐ時は頑張って泳ぐ感じになります。
それはそれで運動になりそうですが、ホースのままだと万が一ホースが外れたりすると問題です。ビオトープ側の水槽は水がなくなることはないのですが、アクアポニックス側の水が干上がってしまいます。
水面を細い水でパシャパシャさせれば、水中の酸素量も上がるだろうしメダカが頑張って泳がないと行けないような水流の場所もなくすことができます。
物理ろ過
当初、ビオトープ側の底石やアクアポニックス側のセラミックの生物ろ過をするリング状のフィルターのみで問題ないと考えていました。
しかし、メダカを入れて1週間もしないうちにメダカは卵を毎日のように産みます。現在は7匹のメダカが泳いでいますが、卵が孵化し稚魚が元気に育つと結構なメダカの量になる気がします。
メダカの糞以外に切れてしまった水草なども水質悪化の原因になります。
そういった物を物理的にろ過するものが必要だと思います。
どういう「ろ過装置」を作るのか
- 固形物をろ過する。
- アクアポニックスやビオトープ側の水面とはあまり差異がないように作る。
- 20Lほどの容量。
- 排水時に水に酸素が混じるように。
物理ろ過装置を自作する
アクアポニックスな水槽から吸い上げた水を、ろ過装置の底に送りオーバーフローした分の水をメダカの水槽に送る物理ろ過装置を作ります。
ろ過装置は、水槽の水面とあまり差異がないように作ります。電源がないため水ポンプが非力なためです。
準備したもの
箱(BOX)
まずは、充分な容量のBOX探しをしました。中には水が溜まりっぱなしになるのでそれなりに丈夫そうな物を選びました。
衣装ケースも良さげな商品がありました。透明なので中の状態も見えるし金額も半額くらいなので迷いましたが、丈夫そうなトランクカーゴを選びました。
容量も22Lあるので恐らく充分かと思います。
猫よけのトゲトゲシート
ポンプから送られてきた水がスムーズに排出されるよう排出口にはフィルター類が入らないようにスペースを作りたいので、猫よけ用のトゲトゲシートを使います。
ろ材
百均に売っている綿と、以下の目の荒いマットを購入しました。
活性炭
ホームセンターにネットに小分けされ、たくさん入っている商品があったのでそれを購入。物理ろ過が目的だけど生物濾過も期待したいです。
塩ビパイプやジョイント
その他塩ビパイプやそのジョイントを購入。エルボやT字にジョイントする物を購入。
容器に穴を開ける
まずは、蓋に穴をあけます。ここから容器の底の方にアクアポニックス側から送られてきた水を送り込みます。


容器の底の方にしっかり水が送り込まれるよう塩ビパイプを底の方まで届くようにジョイントし塩ビパイプの先にはT側のジョイントを取り付け、排水口が容器の底と平行になるようにしました。
排水口が複数あったほうが万が一何かが詰まり水が送り込まれなくなるリスクも減ると思います。そして、容器の底の方にあわよくばメダカの糞などの固形物が沈殿してくれないかな・・とも期待してT時のジョイントを取り付けました。
容器の側面に穴を開ける
容器のなるべく上の方に穴をあけます。ここより上の上澄みがビオトープ水槽に送り込まれます。

この部分は、水漏れしないようパッキンを挟みしっかり対策をしました。

ろ材などを投入
まず、猫よけのトゲトゲマットをそこに丸めて入れます。中央部分は排水口が入るようにスペースをあけておきます。
ここで出来るスペースに、メダカの糞などの固形物が沈殿してくれるといいなと思い広めにしました。
また、ろ材などが排水口を塞ぐことも防止します。

荒めのフィルター
塩ビパイプを猫よけのトゲトゲシートで作った真ん中に入れそれを抑えるように荒いフィルターをいれます。
ここで大きい固形物をろ過します。
綿
次に綿のフィルターをいれます。百均で購入した綿一袋分いれました。

活性炭
最後に、綿を抑えるように荒目のフィルターで抑えた後に活性炭を乗っけました。今回の目的は物理ろ過ですが、生物ろ過も見込んでいます。

排水用のパイプにエルボ
ろ材などが排水用の口を塞いでしまうと容器から水が溢れ出てしまいます。容器には少し余裕があったので、エルボを取り付けました。
ほんの少し水量を稼ぐことが出来るし、口が横よりは上向きにしたほうが何かが詰まるということを防ぐことが出来ると思います。
動かしてみる
容器に水をいっぱい入れてから蓋に取り付けた口に、ポンプから着ているホースを突っ込みます。可能な限りホースはそこの方まで刺しこみます。

ポンプの電源を入れると徐々に水位が上がり、無事塩ビパイプで作ったシャワーから水が出てきました。
動画のシャワーはまだ細すぎたので後から穴を大きくしました。そして、穴が詰まるとろ過装置から水が溢れ出てしまいます。
シャワーの末端の方の数個の穴はかなり大きめをあけておきました。
フィルターの目詰まりは、シャワーの水量を毎日確認し水量が少なくなったと思ったら、フィルター掃除をします。
透明度が上がりました
物理ろ過装置を動かし始めた翌日は、劇的に水の透明度が上がりました。数千円で良いものが出来ました。





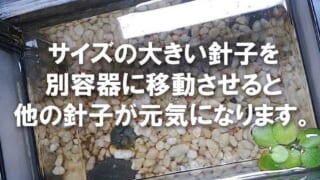





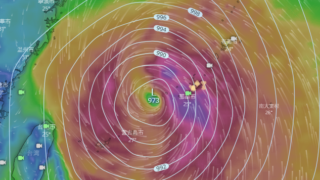









コメント